【7年7月度 産業懇談会(木曜G)模様】
テーマ: 『 ダイセーグループと私 』
- 日 時:令和7年7月3日(木) 12時00分~14時00分
- 場 所:名古屋観光ホテル 3階 桂の間
- 参加者:26名
田中 毅(たなか たけし)氏
ダイセー倉庫運輸株式会社
取締役社長
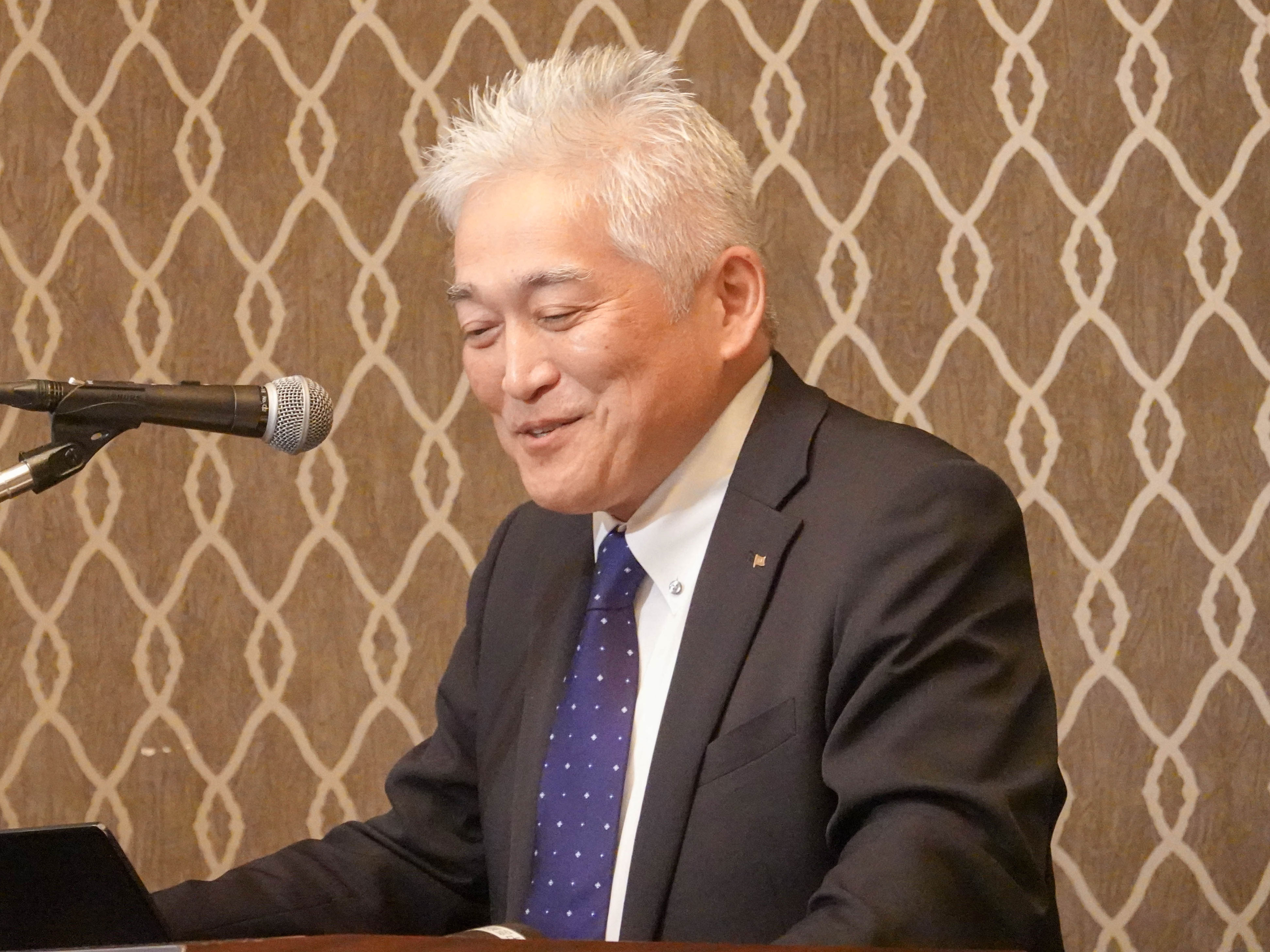
自己紹介と人生観
名古屋市東区在住で3人の娘の父親でもある。長女は名古屋で保育士をしていて、次女、三女は東京で働いている。
私が生まれたのは東京・台東区千束、母の実家がそこにあった。東京で生まれ、東京で育ち、大学は湘南工科大学情報工学科を卒業。最初の就職先は大手運送会社で、物流の現場を経験した後、父親の経営する1998年にダイセーロジスティクスに転職。2009年から愛知に引っ越しをして、ダイセー倉庫運輸に勤務し、2024年に代表取締役社長に就任した。
趣味は「一之宮巡拝」とお薦めをしていただいたところを「食べ歩き」すること。神社仏閣を巡る中で各地の文化や信仰に触れることを楽しみにしている。ダイセーグループの若手を20名連れて、三重県鈴鹿市椿大神社で毎月滝行に参加している。この滝行は、父親が20年続けて行っており、その後私が引き継ぎ10年以上続けている。経営という立場に身を置く中で自らの軸を保つ重要な行為であるとともに新しいことに一歩踏み出す訓練であると考えている。
座右の銘は、松原泰道師の「花が咲いている。精一杯咲いている。私たちも精一杯生きよう」、葉上照澄大阿闍梨の「ポストにベストを尽くそう」である。いずれも人生や仕事に対する真摯な心構えや姿勢が大切であることを教えてくれる。
ダイセーグループ
ダイセーグループは1969年に創業し、「一隅において、キラリと光る存在になる」という理念を掲げてきた。現在は44社のグループ企業を擁し、従業員数は7,500人以上、車両台数は3,800台、倉庫面積は12万坪を超える規模に成長している。
事業領域は大きく分けて、食品・外食産業向けの3PL(サード・パーティー・ロジスティクス)、化学品輸送の3PL、ドライ輸送の3PLである。これに加えて、ITやベーカリー、ホテルなどのサービス業も展開し、多角化経営を推進している。
多くの大手企業様とお取引させていただいており、グループ全体として、単なる物流業ではなく、顧客の供給網全体を支えるパートナーとしての役割を担っている。
この根底には、「荷物ではなく、お客様の“想い”を運ぶ」という“Golden Package”の精神がある。物流を通して社会とのつながりを生み出し、人々の暮らしを支えるという誇りを全社員が共有している。
不動産事業による富の再分配
こうした状況に対し、当社は「富の再分配」を企業戦略の根幹に据えている。その中核となるのが、不動産の小口化・共有化を通じて、資産保有の門戸を広げる取り組みである。これにより、個人や中小企業でも都市部の不動産を持っていただけるようにしている。
また、当社は不動産販売というより企業戦略の提案をしている。従来、各社では本業が一番大切とされていた。しかし、本業に連動しない事業が必要であり、本業でリスクが発生した際に影響を受けない収益部門が必要であると考えている。そこで、自社保有物件からの賃料収入にも注力している。実際、全売上の1割未満に過ぎない賃料収入が、経常利益の約半分を構成しており、これは危機時においても企業活動を支える重要な柱となっている。
「貸事務所業」は創業100年以上の企業が多く属する業種であり、長期的視点での安定経営を象徴している。不動産の中でも「貸す」という行為はリスクを抑えつつ、複利的に企業価値を積み上げることが可能である。
たとえば、都心に10億円の不動産を保有し、年率5%で価値が上昇すると、100年後には1,300億円規模の資産になる計算となる。これは、単利で積み上げる事業利益とは異なる「複利」の力であり、企業戦略に取り入れることで世代を超えた価値創造が可能になる。
人材育成と企業文化
ダイセーグループでは、「Smile & Clean(挨拶と清掃)」という考えを大切にしている。さわやかな挨拶と洗車されたトラック、気持ちのよい職場環境と、信頼される職業人としての基本行動を徹底し、企業文化として根付かせている。
また、「One on One Meeting」を通じて、上司と部下の間で相互理解を深める仕組みを構築している。単なる業務報告にとどまらず、部下の人生観や価値観にも寄り添うことで、組織の一体感を育んでいる。また創業時は現場で働くドライバーに向けて、「子どもを大学に行かせよう」「持ち家を持とう」「新聞や本を読んで尊敬される人間になろう」という3つの目標を掲げている。これは職業としての誇りや生活基盤を高めるとともに、仕事を頑張って人生を作っていこうという意識を持ってもらうためのものである。物流業の現場は、単なる作業の場ではなく、人が成長し人生を築く場であるべきだと考えている。
ダイセー倉庫運輸の新しい取り組み
私が現在いるダイセー倉庫運輸は、1972年ダイセーグループが創業間もない頃、私の父親がまだドライバーをしていた時に名古屋の納入先の倉庫で加藤俊夫という人間と出会い、あまりに素晴らしい青年だったために悩んだ末に一緒に会社をやらないかとスカウトした。お互いに大変意気投合し、加藤俊夫は初代社長としてダイセー倉庫運輸の創業をすることとなった。
ダイセー倉庫運輸では7月7日、小牧市に新たな物流拠点「JILP(Just Intelligence Logistics Plaza)」をオープンする。延床面積は約9,500坪、製品の積み下ろしを倉庫内で行う仕様となっている。また40フィートの海上コンテナを12台同時接車可能なコンテナバースを備えていること、15600パレットの移動ラックで生産性と品質を確保していることがこのセンターの特徴。
昨年、「2024年問題」という言葉が話題になったが、この施設はドライバーの時間外労働規制に対応する戦略的拠点と位置づけており、共同配送や積載率の向上、荷待ち時間の削減などを通じて、生産性とコンプライアンスの両立を目指している。
また、太陽光発電設備を導入するなど、再生エネルギーを積極的に活用し、環境にも配慮した設計を行っており、サステナブルな物流を実現するためのモデルケースにもなる見込みである。
この新しい物流拠点JILPは、これまでの50年に感謝をして、次の100年を目指して進んでいくセンターです。ダイセー倉庫運輸の理念である「朝起きたらすぐ行きたくなる会社を作りましょう!明るく!楽しく!そして逞しく!」を胸に全社員全クルーでポリマー品の共同配送であるジャスト便を前へ上へと進めていきたい。
【7年7月度 産業懇談会(火G)模様】
テーマ: 『 簡単なゴルフの歴史とヒッコリーゴルフ 』
- 日 時:令和7年7月8日(火) 12時00分~14時00分
- 場 所:名古屋観光ホテル 3階 桂の間
- 参加者:41名
スピーカー:
中日本興業株式会社 顧問 小塚康氏(水曜第2グループ)のご紹介

JAPAN HICKORY GOLFING SOCIETY 会長
中日本興業株式会社 代表取締役社長

JAPAN HICKORY GOLFING SOCIETY 幹事長
<JAPAN HICKORY GOLFING SOCIETY 会長 服部徹氏>
ご挨拶
本日は、このような貴重な場においてヒッコリーゴルフの魅力についてお話しができることを、大変光栄に思う。現在、映画「国宝」がヒットするなど、日本でも伝統的な文化や美意識が見直されており、ヒッコリーゴルフもまた、古き良きゴルフの文化を現代に受け継ぐものであると感じている。
私自身、もともと古い道具が好きだったこともあり、3年前にヒッコリーゴルフを始めた。実際にプレーしてみると驚くほど自然に、そして肩肘張らずにゴルフが楽しむことができた。和気あいあいと、ゴルフ場に吹く風や景色、ニッカポッカやハンチング帽といった100年前のスタイルで楽しみながらプレーできるのも魅力のひとつ。スコア110のプレイヤーでも、ヒッコリーなら楽しくラウンドできるということを、私の体験からお伝えしたい。飛距離を求めてクラブを購入することもなくなり、経済的でもある。
当会で幹事長を務めている福本氏は、ヒッコリーゴルフ日本代表を4連覇に導いた監督兼プレイヤーでもある。福本氏からの話を聞いて、ヒッコリーゴルフについてぜひ興味を持っていただけたらと思う。
<JAPAN HICKORY GOLFING SOCIETY 幹事長 福本勝幸氏>
ゴルフの起源と近代ゴルフの発祥
ゴルフの起源は、紀元80年に古代ローマ帝国がスコットランドを征服した際に行われた「パガニカ」という遊びにあるとされている。この球技は、羽毛を詰めた革製のボールをこん棒で打ち、飛距離を競うというシンプルなものだった。約300年にわたるローマの支配を通じて現地に定着し、後世のゴルフへとつながっていく。なお、現在でも使われる「クラブ(club)」という言葉は、古英語で「こん棒」や「武器」を意味しており、語源の観点からもこの説は非常に有力とされる。
中世に入ると、類似の打球遊びがヨーロッパ各地に広まっていく。1300年代にはイギリスで「カンブカ」、1400~1700年代にはイタリアやフランスで「ジュ・デ・メル」や「ポール・モール」などが流行。これらは、長い柄の木槌を用いて、木製のボールを数百メートル先の目標にいかに少ない打数で到達させるかを競うもので、現代のゴルフと共通する要素を備えていた。
中でも、1200年代にフランダース(現在のオランダ)で行われていた「コルベン」または「コルフ」という球技が、近代ゴルフの最も直接的な原型とされている。凍った平地で、革製ボールを15メートルほど先のターゲットに当てるというこの遊びは、14世紀以降スコットランドに伝わり、特にセントアンドリュースの海岸でオランダ人とスコットランド人の間で盛んに行われるようになった。ボールが高価で水に弱かったため、やがて遊び場は海岸から草地へと移され、広大なリンクスランドがコースとして使われ始めた。
こうした背景のもとで、ゴルフという呼称も生まれたと考えられる。もともとゲルマン語で「コルフ」と呼ばれていたものが、スコットランドにおけるゲール語なまりで「コウフ」→「ゴウフ」へと変化し、最終的に「ゴルフ(Golf)」という言葉として定着したと推測されている。
木製シャフトとヒッコリークラブの魅力
ゴルフが海岸沿いのリンクスランドで定着すると、より遠くへ正確に球を飛ばす必要が生じ、それに伴いクラブの素材や構造も進化していった。ヘッドは小さく硬く、シャフトは細く長く、そしてしなりの良いものへと改良され、同時にボールもより硬く丈夫なものへと変化していった。
15世紀から19世紀にかけての約400年間、ゴルフクラブはヘッドとシャフトが一体で作られていたが、時代とともにさまざまな木材が世界中から使われるようになった。1492年、コロンブスが南米に到達すると、クスノキ科のリョクシンボクが素材として注目され、18世紀にはジェームズ・クックによって調査されたニュージーランドのランスウッド、19世紀には日本のトネリコなど、地域ごとの木材が加工技術とともに取り入れられていった。
1830年頃には、ヘッドとシャフトを別々の素材で組み立てる技術が確立され、特にヘッドには北米産のパーシモン(柿)、シャフトにはクルミ科のヒッコリーが最も適していることが明らかとなった。この組み合わせにより、耐久性、しなり、加工のしやすさといった実用面での理想が実現し、現在のクラブの原型となる構造が整った。
また、19世紀後半には「ロフター」や「ラットアイアン」といった鉄製のヘッドが登場し、合わせてガタパーチャ製のボールも開発され、モダンゴルフの基礎が完成していく。スチールシャフトが登場する1935年頃までは、約500年にわたって木製シャフトが主流であり、特にヒッコリークラブはその象徴とも言える存在だった。
現在では、ヒッコリークラブはゴルフの伝統や歴史に触れるツールとして見直されつつあり、クラシックなスイングやマナー、ファッションとともに当時のゴルフ文化を再体験できる貴重な道具とされている。
世界初のゴルフクラブとゴルフ文化の広がり
近代ゴルフの制度化は18世紀中頃に始まる。1744年、スコットランド・リースの「Leith Links」という5ホールのコースに、世界初のゴルフ倶楽部「Gentlemen Golfers of Leith」が創設された。このクラブでは、世界で初めて13ヶ条のゴルフルールが制定され、それに基づく公式競技が開催された。初代優勝者ジョン・ラトレーは、そのままクラブのキャプテンに就任し、これが世界最初の「ゴルフクラブのキャプテン」となった。
当時のエジンバラ行政府からは、優勝者への記念品として銀製のゴルフクラブ「Silver Club」が贈られ、このトロフィーを巡る年次大会が恒例化する。このSilver Clubをきっかけに、1754年にはセントアンドリュースのゴルファーたちが「Society of St. Andrews Golfers」を結成。これが後に「Royal and Ancient Golf Club of St Andrews(R&A)」と名を変え、現在もゴルフ界の最高権威のひとつとして存続している。
一方、「Gentlemen Golfers of Leith」は、都市化によってLeith Linksが公園化されたことに伴い、近隣の競馬場内にあるマッセルバラ・リンクスに移転。その後、競馬開催日にはプレーできないという制約もあって、1891年にミュアフィールドに最終移転し、名称も「Honourable Company of Edinburgh Golfers」と改められた。現在では全英オープンの開催地として世界中のゴルファーに知られ、2年待ちの予約が必要な人気コースとなっている。
なお、日本で「ゴルフは紳士のスポーツ」と言われるようになったのは、このクラブ名にある“Gentlemen”の語を「紳士」と訳したことによる。しかし、本来18世紀の“Gentleman”は、社会的地位を示す階級用語であり、領主や弁護士、医師などの特定階層を指していた。1903年に神戸で日本初のゴルフ倶楽部が設立された際には、この意味が「品格と教養を備えた人」と解釈され、やや誤って「紳士のスポーツ」というイメージが定着した。
それでも、現在のゴルフにおいては、エチケットやマナーが最も重視されるという文化は世界共通であり、特にアマチュアゴルファーにとっては「紳士的に振る舞うこと」が常に求められている。実際、ゴルフの聖地セントアンドリュースでは、マナーの悪い富裕層は受け入れられず、エチケット最優先の姿勢が貫かれている。
【7年7月度 産業懇談会(水曜第2G)模様】
テーマ: 『 留学生活用事例~定着率90%超のヒミツ~ 』
- 日 時:令和7年7月9日(水) 12時00分~14時00分
- 場 所:若宮の杜 迎賓館 1階 橘の間
- 参加者:25名
塚本 将弘(つかもと まさひろ)氏
株式会社Harmony For
代表取締役

自己紹介と起業のきっかけ
私は名古屋大学大学院工学研究科の出身で、在学中は工学の研究に励む一方、世界を見たいという思いから世界一周の旅に出た。訪れた国々で教育格差や雇用の不平等に直面し、多様性が尊重される社会の重要性を痛感した。特にインドやアフリカ地域での教育へのアクセスの困難さ、若者たちの希望と不安が交錯する姿が深く心に残った。
帰国後、名古屋大学で留学生のチューターとして活動する中、外国人留学生が直面する多くの課題に触れた。「就職先が見つからない」「日本語の壁が高い」「頼れる人がいない」といった声に、せっかく日本で高度な教育を受けたにも関わらず活躍の場がない現実を見て、解決すべき社会課題だと感じた。
その後、仲間とともに学生団体を立ち上げ、交流イベントやアルバイト紹介、進路相談などを行うようになった。この経験が後の起業の原点となり、2016年、大学発ベンチャーとして「株式会社Harmony For」を創業した。名古屋大学Tongaliプロジェクトの支援を受け、全国規模で外国人留学生と企業をつなぐマッチング事業を展開している。
活動の根底にあるのは、私自身の原体験である。高校時代には研究に没頭し、トライボロジーの学会での発表経験もあった。しかし、学外に出て世界を旅したことで、自らの価値観が大きく揺さぶられた。特にインドでダライ・ラマ氏と対面した経験や、ストリートチルドレンとの交流を通じて、教育と貧困の問題を体感した。中国では歴史問題をめぐる対立にも直面し、「日本人としての視点」だけでは通用しない現実を知った。
そうした体験から、「誰もやっていない社会課題に挑むこと」「困っている人の力になること」「差別や格差に目を向けること」が私の行動の指針となった。Harmony Forの理念も、ここに由来している。
Harmony Forのサービス概要と特徴
当社の主力サービス「Job Tree Japan」は、日本語が話せる外国人留学生と日本企業をつなぐ就職支援プラットフォームである。全国50以上の大学と連携し、2万人超の留学生データベースを有している。中でも理系の学生が47%を占めている。
特徴は以下の3点。
- 独自開発のマッチングアルゴリズム
入社後3年間の定着率は97%を誇る。この成果は、スキルだけでなく文化適応や企業風土との相性、キャリア志向など多面的に評価しているためである。 - メンターによる個別支援
留学生一人ひとりに担当メンターを付け、ビザ申請や住居探し、日本語学習、悩み相談までを一貫して支援している。 - 大学・企業との密接な連携
大学とは定期的に連携し、ガイダンスや面接練習を実施。企業には求人票作成や広報支援を行い、ミスマッチの防止に努めている
学生と企業、双方のニーズに基づく支援事例
- 事例① 製造業
理系人材の確保に苦労していた同社に、ブラジル人・スリランカ人の留学生を紹介。日本語教育やマネジメント支援を実施し、3年後には役員から高い評価を受けている。 - 事例② 自動車部品メーカー
初年度6名の採用から始まり、現在は15名以上が活躍。多国籍の人材が海外事業の展開や社内DX推進に貢献している。 - 事例③ 商社
社内のDX化を進めたいが、システム人材が不足していた企業に、インドネシア出身の情報系人材を紹介。社内SEとして活躍し、業務改善に貢献している。 - 事例④ 海外拠点立ち上げ
インドに進出するにあたり、日本語が話せるインド出身の営業人材を紹介。現地の日系企業対応を担い、事業展開を後押ししている。
このように、地方企業や中小企業が抱える「人が採れない」「海外進出が不安」といった悩みに対して、多くの企業と留学生をつないできた。
今後の展望
今後注力していきたいのは、地方製造業における理系人材の確保、グローバル展開に対応できる人材の育成とマッチング、日本語教育や文化適応を含む定着支援の強化、財務・法務・監査など専門職分野への外国人材活用などである。
外国人留学生の活躍の場を広げることは、日本の労働力不足の解消策であり、企業の国際競争力を高める手段でもある。特に日本では理系志望者の減少が続いており、採用戦略の見直しが急務となっている。多様性ある社会と次世代の組織づくりを進めていきたい。
【7年7月度 産業懇談会(水曜第1G)模様】
テーマ: 『 自己紹介~読書『俺たちの昭和後期』の感想を添えて~ 』
- 日 時:令和7年7月16日(水) 12時00分~14時00分
- 場 所:名古屋観光ホテル 3階 桂の間
- 参加者:24名
安部 源太郎(あべ げんたろう)氏
ユニオンテック株式会社
取締役社長

今回は私の「自己世代の紹介」をテーマにお話をさせていただきたい。
きっかけとなったのは、北村朋広さんの著書『俺たちの昭和後期』である。読み進めるうちに、自分の少年時代が鮮明に蘇り、思わず「これは自分の話ではないか」と錯覚するほどの共感を覚えた。まさに、あの時代を生きた者同士にしか分からない、熱とノスタルジーが詰まった一冊である。
私は昭和41年生まれで、著者とほぼ同世代。ちょうど昭和後期と呼ばれる時代を、小学校期として過ごした。日本が戦後復興を経て高度経済成長を遂げ、生活や価値観、文化が急速に変化していった時期だった。
昭和後期の幕開け──カラフルな社会の到来
昭和46年、三島由紀夫の割腹自殺という象徴的な事件が起きた翌年から、昭和後期が本格的に始まったとされている。この頃、生活の中に「色」が入り込んできた。NHKがすべての放送をカラー化し、大阪万博が開催され、街中がカラフルな看板や商品で彩られていった。
銀座三越にオープンしたマクドナルド1号店や、カップヌードルの登場もこの頃だ。今でこそ当たり前のこれらの“アメリカ的”ライフスタイルは、当時としてはまさにカルチャーショックだった。大人たちは眉をひそめつつも、子どもたちは「新しさ」にワクワクしていた。ファストフードを食べることが、ある種の“時代の先端”を感じさせる体験だった。カップヌードルといえば、浅間山荘事件で機動隊員が現場で湯気を立てながら食べる映像がテレビ中継され、大きな話題になった。国家的な事件の裏で、ひとつのカップラーメンが時代を象徴するプロダクトとなった。
「正義」と「根性」が価値だった時代
テレビや漫画の影響力は絶大だった。仮面ライダー、ウルトラマン、巨人の星、明日のジョー……。これらの作品は、単なる娯楽ではなく、「どう生きるか」というメッセージそのものだった。
仮面ライダー1号こと藤岡弘がスタントなしで戦ったというエピソードに象徴されるように、正義のために身体を張る、その“覚悟”に憧れた。巨人の星の星飛雄馬は、父のスパルタ教育のもと野球に命をかける姿が描かれ、「涙を見せるな」「努力は裏切らない」といった“昭和的精神論”を体現する存在だった。
ドリフターズの『8時だョ!全員集合』では、チームワークの大切さ、仲間の信頼、体当たりのパフォーマンスなど、笑いの中に“学び”があった。志村けんの加入以降、ドリフの完成度はさらに高まり、「連帯責任」や「全員が欠かせない」という価値観を、我々に刷り込んでいった。
今思えば、テレビの中の「正義の味方」たちは、親や先生とは別の“もう一人の教育者”だったのではないかと感じている。
遊びとモノから得た感性と社交性
当時の遊びは、今と違って“みんなで遊ぶ”のが基本だった。エポック社の野球盤、仮面ライダーカード、超合金マジンガーZ──これらのおもちゃは、ただの物ではなく、友達との関係性を育む道具でもあった。
ゲームもまた進化し、スペースインベーダーやファミコンへと続いていった。アナログからデジタルへの移行を体験したことで、我々は“両方の感性”を自然と身につけた世代だと思っている。情報が手軽でなかったぶん、創造力を膨らませて遊ぶ力、すなわち「妄想力」「工夫力」が育まれていた。
当時の製品には、「所有する喜び」「欲しいものを我慢して手に入れる達成感」があった。仮面ライダーベルトやローラースルーGOGOといった高価な玩具は、誕生日やクリスマスにやっと手に入る“特別なもの”だった。
車とバイク──物欲と夢の象徴
スーパーカーブームも忘れられない。『サーキットの狼』を読んでロータスヨーロッパに憧れた小学生たちは、ランボルギーニやフェラーリの消しゴムをボールペンで飛ばして机上でレースをしていた。小さな玩具に“夢”を詰め込むその感性は、現代のデジタルネイティブ世代とはまた違う「アナログ的豊かさ」だった。
車やバイクは、単なる移動手段ではなく、「男として一人前になるための証」でもあった。ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ──4大メーカーの技術競争の裏には、ユーザーである我々の“欲望”があった。仮面ライダーに憧れてバイクに乗ったように、我々は「文化としての乗り物」に育てられた世代だと感じている。
音楽、テレビ、そして“昭和の空気”
『ザ・ベストテン』や『夜のヒットスタジオ』、サザンオールスターズ、RCサクセション、YMO──当時の音楽番組は、視聴者を“共犯者”として巻き込む力があった。ランキングにドキドキしながら出演者を応援し、衣装やパフォーマンスを真似して盛り上がった。まさに“参加型のカルチャー”だった。
テレビの中の“先生”も印象的だった。『3年B組金八先生』では、厳しさの中にある優しさ、社会の中で弱さを抱える生徒たちへのまっすぐなまなざしが、心を揺さぶった。あのドラマに育てられたという同世代も多いはずだ。
昭和後期世代の“熱”を、次の時代へ
我々、昭和後期世代は、戦争を知らず、貧困を知らず、しかし文化の奔流の中で育った。テレビ、音楽、漫画、商品、玩具──すべてが成長と共にあった「時代の教師」だった。
いま、SNSやコンプライアンスの時代になり、かつての表現や価値観が“修正”されることも多いが、当時の熱や混沌を、単なるノスタルジーとして終わらせてはいけないと感じている。
不確実な時代だからこそ、「汗を流すこと」「仲間を信じること」「夢を語ること」──あの頃、我々が自然に育んできた精神が、次の時代を支える“熱源”になるのではないか。そう信じている。
昭和後期とは、情緒あふれる日本人が紡ぎ出した、熱のこもった愛の時代であったように思う。
【9月度産業懇談会のご案内】
日頃は産業懇談会活動につき多大なるご支援をいただき誠にありがとうございます。
9月度例会を下記の通り開催いたしますので、ご案内申し上げます。各グループ興味深いお話が伺えるものと存じますので、ぜひともご出席くださいますようお願い申し上げます。
| グループ名 | 世話人 | 開催日時 | テーマ・スピーカー | 集合場所 |
|---|---|---|---|---|
| 火曜グループ |
屬ゆみ子 |
9月9日(火) |
【外部講師ご登壇】 |
名古屋観光 |
| 水曜第1グループ |
足立 誠 |
9月17日(水) |
『公共下水道 ~出遅れた維持管理~』 |
若宮の杜 |
| 水曜第2グループ |
香川裕子 |
9月10日(水) |
『名刺を起点とした顧客データベース構築による、企業の収益の最大化について』 |
若宮の杜 |
| 木曜グループ |
河村嘉男 |
9月4日(木) |
『視察会「ノリタケの森」』 |
名古屋市西区 |
【産業懇談会4グループ合同懇親会
のご案内】
平素は中部経済同友会・産業懇談会の活動にご支援を賜り、誠にありがとうございます。
恒例の4グループ合同懇親会について下記のとおりご案内申し上げます。
今回は木曜グループの企画により、ジャンルを超えて音楽の魅力をお届けする「クラシックとジャズの夕べ」を開催いたします。
実力派演奏家&歌い手の皆さまをお迎えし、それぞれのジャンルによる音楽の深さと広がりをご堪能いただきます。一夜限りの特別な音楽会をお楽しみいただきたく、ぜひ多数の皆さまにご出席賜りますようお願い申し上げます。
- 日時
- 2025年10月16日(木) 17:30~20:00
- 場所
- 名古屋東急ホテル 3階 バロック (名古屋市中区栄4-6-8/TEL: 052-251-2411)
- 会費
- お一人 14,000円内外(後日、実費をご請求させていただきます)
- スケジュール
- 17:30~18:30 公演「クラシックとジャズの夕べ」
第一部 クラシック『心に沁みる名曲集~バッハから美空ひばりまで~』
演奏 Masaco西嶋(ピアノ)、村越久美子(ヴァイオリン)
山田真吾(チェロ)
第二部 ジャズ『1960年代のオールドクラシックスタンダードジャズ』
演奏 Masaco西嶋(ピアノ)
歌 生田サリー、河村嘉男 - 18:40~20:00 懇親会(着席ビュッフェ)
- 17:30~18:30 公演「クラシックとジャズの夕べ」
- 申込方法
- 10月7日(火)までに会員専用ページからご登録をお願いいたします。
- お申し込み後のキャンセルは、10月9日(木)17時までにお願いします。
期日以降は会費を申し受けますので、あらかじめご了承願います。
- 問い合わせ先
- 担当:羽根田、山田 Tel:052-221-8901 FAX:052-221-8925
E-mail:cace-seminar@cace.jp
【コラム】
コラム1 【さっかの散歩道】 No.86
長瀬電気工業株式会社
代表取締役 屬 ゆみ子
『 マニア 第九を歌う 』
5月の終わり、友人に誘われて、鳴門にベートーベンの第九を歌いに行ってきた。
第九の合唱は、歌ったことのある方ならお分かりだろうが、ドーパミンが出まくるので、演奏後には達成感と清々しさに包まれて、中には感極まって涙する方もおられるほど。なので中毒性があるらしく、日本中の第九の演奏会を見つけては参加するという強者もいる。おあつらえ向きに、日本は世界中で、年間の第九演奏会が一番多い。毎回合唱メンバーを、各パート合わせて200人から一万人まで募集をかけるのだから、プチ旅行も兼ねて出かけるにはちょうど良いらしい。
鳴門の第九は恐らく一年のうち一番最初に演奏されていると思われる。年末のイメージがあるのに何故?と思われるかもしれないが、実は鳴門はアジアで一番最初に演奏された場所なのだ。1918年6月、第一次世界大戦のドイツ兵捕虜が、鳴門の収容所で演奏したのが始まりで、以来鳴門では6月1日を「第九の日」と定めており、平成元年には「全日本第九を歌う会連合会」なるものが設立されている。そういう所縁のある場所なので、日本中の第九マニアが集まってくるのだ。となれば、ちょっと興味深く、車を飛ばして参加した。
そもそもベートーベン本人による初演は1824年5月7日。フランス革命の翌年、ウィーンにあるハプスブルグ家の宮廷劇場を借りて、手弁当で演奏会を開いたらしい。とはいうものの参加メンバーは劇場付きのオーケストラと合唱団、リハも念入りに行い、大喝采を受けたという…一部後日談では、この時すでにベートーベンはほとんど耳が聞こえなかったと言われているが、実は聞こえていたと証言する演奏家もいたりして、どうやら彼の人生は色々ドラマティックに書き換えられてるらしい。余談だが9月には「ベートーベン捏造」という映画が上映されるそうだから、その一面が垣間見れるかも!ついでに言うなら、ベートーベン全集を書いたのは属 啓成で、大大叔父に当たる。

以前も少し触れたのだが、私は何を隠そうドイツ語の歌が苦手で、出来るだけ避けているが、第九だけはオーケストラの構成―第4楽章に向かって求める美しい場所へと、観客を歌が誘って、演者と共に大団円を迎える、が面白く、合唱席から高揚してゆくお客様を“シメシメ、してやったり”と見ているのが楽しい。それに加えて、まるで天使が舞い降りるかのような第3楽章には、毎回うっとりさせられる。合唱団は第1楽章から、着席して4楽章を待つのだが、大体3楽章まではスヤスヤくつろいでいる方も多く、時々イビキも聞こえ、特に3楽章はそれくらい平穏なのだが、4楽章の不協のファンファーレが響くとみなさんギアが一気にトップに入る、お目覚めすぐに歌えるのは、マニアの為せる技で感心しきり。

演奏会参加証
今回の鳴門は、記念すべき41回だったのだが、コンサートホールが改装中のため、鳴門教育大学の体育館での演奏となった。体育館で歌うのは初めてだが、流石にオケと合唱のバランスがあまり良くなく、マエストロに「元気に歌い過ぎないで(オケの音が聞こえない)」と言われたが、流石に300人からのマニア、本番でしっかり声出しして、私の隣の方は涙を流しながら歌っていた。そのせいかどうか知らないが、鳴門第九は新しいホールが出来るまでお休みとなるそうで、記念に参加証など頂いた。
話は変わるが、今回宿探しには苦労した。大学と鳴門北インターの間に、お手頃リゾートホテルがあったので、そこを予約していたのだが、勿論大手予約サイトからの予約だったのだが、一抹の不安~インターの近くのリゾートホテルって…。案の定、元ラブホだった。入口と出口のエレベーターが違うやつ。あ、でもちゃんとレセプションはありましたよ。元ラブホに宿泊するのはこれが2回目。以前御殿場近くで泊まった時には部屋にカラオケがついていた。何よりベットが大きいし、バスルームも無駄に大きい。流石に変な電飾とかはないけど、ルームサービスが、入口横の小窓から届けられるのが笑える、朝うどんが届いた時は、伸びないように気を使ったのか、インターホンを鳴らしてくれた、ある意味ピンポンダッシュだけれど!
次は10月、札幌の999人の第九だ。キテラコンサートホールが改修工事に入るので、この第九もキテラでの歌い納め。なんだかんだで私もすっかりマニアの仲間入りのようだ。
コラム2 【師、曰く】 No.51
蒲郡観光交流おもてなしコンシェルジュ 妹尾 鷹幸(ペンネーム)
(株式会社構造計画研究所 名古屋支社長 妹尾(せのお) 義之)
ペンネームは、恩師、田坂広志先生の多重人格マネジメント、作家人格の名。心に鳴り響く言葉を今回も一筆。
『 成功 』
若かりし頃、漠然と考えていた。私にとっての「人生の成功」とは何だろうと。田坂講義では幾度も耳にした「成功」と「成長」の言葉。田坂塾生は、「成功」を目的とはしない。あくまで「成長」が人生の目的である。それはなぜか。『人生において、「成功」は約束されていない。しかし、「成長」は約束されている。』からだ。社会通念のいわゆる「成功」は、競争社会で勝者となること。当然ながら、「成功」を手に入れられるのは、ほんの一握りの勝者だけだ。どれほど努力しても、競争の過程で失敗や挫折が与えられた大半の人々、いわゆる敗者は、深い敗北感と無力感を味わうことになる。その敗者は人生に敗れ去ったのだろうか?さらに言えば、勝者は人生を勝ち取ったのだろうか? 50歳手前で田坂講義を受けた私は、疑問に感じるようになっていた。力や富を得ることが不幸とは思わない。むしろ、幸福の側に居ると考えるのが普通だ。ただ、時にそれらを持っていても、不満で不幸そうな人達がいる。一方、それらを持っていずとも、満ち足りて幸せそうな人達もいる。それはなぜか。
師、曰く『アメリカの教育世界には、深い言葉がある。“Find your own uniqueness. Define your own success.”』
「あなたにとっての「あなたらしさ」を見つけなさい。あなたにとっての「人生の成功」を定めなさい。」 という社会通念に囚われない生き方の教えだ。この教えには、競争が無い。人と比べる必要が無い。対して、団塊の世代を親に持ち、受験戦争と呼ばれた時代を生きてきた我々世代は、「競争」の思想にどっぷり浸かっていた。一流と呼ばれる大学に進み、一流と言われる大企業に就職し、出世して裕福な家庭を作るという画一的な成功の定義で、当り前のように競争し、人と比べて生きてきた。私も勝ち負けに拘り、受験戦争を戦った。営業マン時代はトップ営業を目指して奮闘した。受験も営業も、ライバルに勝った時は一瞬、心の奥底で密かに笑みが浮かんだ。エゴから生まれた嫌な笑みだった。しかし、そんな競争に空しさを覚えた時があった。いつまでこんな誰かとの勝負に拘り競争し続けるのか。仲間をつくろう、若手をサポートしよう、仲間達と共に成果を上げよう、そう思い立ってから10年以上が過ぎ、今では私個人というより組織レベルの視点で、「競争から共創、そして協奏へ」という思いは信念に近いものに変わった。私らしさを明確な言葉で見出せてはいないが、私の「人生の成功」とは、競争して勝つことではなく、共創し少しでも周囲をより良い方向へ変え、皆で美しい協奏を創り出すことだと思うようになった。
社会通念の成功であれ、自ら定義した成功であれ、失敗や挫折はこれからもあるだろう。しかし、競争に敗れた空しい敗北ではなく、美しい音色を目指す協奏の過程での不協和音ならば、またやり直して奏でれば良い。その思いが失敗や挫折から這い上がる支えとなる。いつか必ず美しい音色で協奏できる日が来る。そして、田坂先生の言われる深い意味のある、『成長』に繋がってゆく。その『成長』については改めて。修行は続くよ、どこまでも。最後までお読み頂き、ありがとうございました。

コラム3 【げんき通信】 No.24

学校法人佑愛学園
愛知医療学院大学 リハビリテーション学部
リハビリテーション学部 理学療法学専攻
准教授 松田 文浩
『 腰痛予防に欠かせない“腰部多裂筋” 』

腰痛は、多くの人が一度は経験する身近な症状です。その腰痛にかかわる要因は様々ですが、今回は“腰部多裂筋”という筋肉に注目してみましょう。
腰部多裂筋は、腰の高さで背骨のすぐ両側にある筋肉です。体幹を支えるインナーマッスルのひとつです。この筋肉は腰を動かすだけでなく、腰部を安定させ、姿勢を保つために欠かせない存在です。
ところが、腰痛のある方では、この腰部多裂筋が硬くなったり、弱くなったりすることがわかっています。特に腰痛を発症した直後にはこの筋肉が急速に萎縮し、自然には回復しないと言われています。こうして弱くなってしまうと腰の安定性を損ない、再び腰痛を引き起こすといった悪循環につながります。
そのため、腰部多裂筋を意識的にほぐし、また鍛えることは腰痛の予防にとても大切です。今回は自宅でもできる簡単な方法を紹介します。なお、痛みがある場合は行わないようにしてください。

まずはストレッチです。四つん這いになり、背中を丸めたり反らせたりします。この運動は、腰椎周囲の柔軟性を高め、多裂筋を含めた筋肉の緊張を和らげます。腹筋に力を入れながらしっかり背中を丸めるのがポイントです。呼吸を止めずにゆっくり行いましょう。

次に強化です。四つん這いの姿勢から片腕と反対の脚を同時に持ち上げて伸ばします。伸ばした腕と脚を床と平行にし、腰もまっすぐに保つことで、多裂筋を中心としたインナーマッスルが自然と鍛えられます。最初は数秒間保持し、慣れてきたら少しずつ時間を延ばしましょう。難しい場合は、腕もしくは脚をひとつずつ持ち上げて伸ばすだけでもOKです。
つらい腰痛を予防するため、無理のない範囲で、ぜひ生活に取り入れてみてください。
